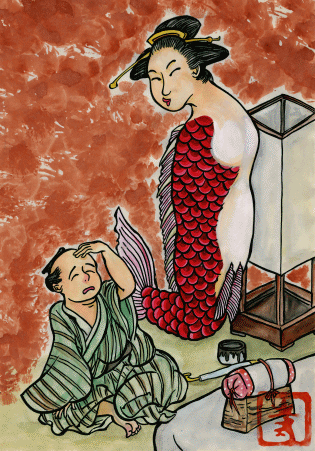
■女房人魚[にょうぼうにんぎょ]
▽解説
山東京伝作、寛政三年(1791)刊行の黄表紙『箱入娘面屋人魚』の登場人物です。
頃は寛政、歓楽街として栄えた日本橋の中洲新地は頻発する洪水のために廃されて元の浅瀬に戻ると、人の支配を離れて龍宮の領分となり、魚族の街として賑わいをみせはじめました。
さて、いつからかその中洲の茶屋「利根川屋」では美しい魚の娘「お鯉(り)の」が働いてました。龍宮を治めていた沙竭羅(しゃがつら)龍王の二代目「ばかつら龍王」の息女乙姫の男妾である浦島太郎は、ひそかに中洲へ通って彼女と深い仲になり、やがてひとりの子を生しました。
生まれた女の子の姿は頭が人、体が魚のいわゆる人魚。龍王にこのことを知られては危険が及ぶと考えて、浦島太郎は不憫ながらも人魚の子を捨ててしまいました。
それから十七、八年後。所変わって神田八丁堀界隈。
沖釣りを家業としている釣舟の平次なる中年男が、品川沖にて成長した人魚の娘に遭遇しました。
その容貌はなかなか美しく、平次も親しげに話しかけられてまんざらでもない様子。やがて平次は「どうぞ、ぬしのかみさんにしてくんな」という人魚の言葉に乗って、そのまま彼女を家に連れて帰りました。
平次は親に捨てられた人魚の不幸な身の上を知って憐憫の情を抱き、訪ね来る見世物師などの誘いも断って人魚を女房としていたわってやりました。
女房人魚は困窮している平次を助けて恩を返そうとあれこれ思案しますが、手足のないに魚の身ではどうも上手くいきません。やがて「舞鶴屋」という女郎屋の主が、平次の留守に人魚をお決まりの七両二分で買い取って女郎にしてしまいました。
そして人魚は「魚人(うおんど)」という名の花魁に仕立て上げられました。着物に包まれ、手足は背後の黒子が動かすことでどうにか体裁を保っているものの、いざ床入りとなればその生臭さに客も逃げ出してしまいます。黒子はどうにか客を離すまいと奮闘するも、当の人魚は疲れてぐっすり眠っています。やがて正体が露見して、舞鶴屋の企ては失敗に終わり、人魚は平次の家に戻ってきました。
その後、ある物知りから「人魚をなめた者は千歳の寿命を保つ」と教えられた平次は、さっそく自宅に「寿命の薬 人魚御なめ所」の看板を出しました。嘗め賃は金一両一分。
なんとこの商売が大繁盛。長生きをしたがる人々が挙って人魚をなめに訪れ、平次は大金を儲けて暮らしに不自由しなくなりました。近所の亭主は女房に鯉のぼりを着せて便乗商売を始めましたが、さすがにこれは流行らなかったようです。
平次自身も暇さえあれば人魚をなめていたところ、あまりになめ過ぎて若返ってしまい、気づけば七歳ばかりの小僧の姿になっていました。そして何やら乳が飲みたい気分に。
亭主は子供、女房は人魚ということで難儀していると、かの浦島太郎が玉手箱を携え、茶屋の鯉を伴って現れました。
玉手箱の効果で平次は再び丁度良い男盛りに成長しました。その後、女房人魚も一皮剥けて手足が生じ本当の人間になり、二人は仲睦まじく暮らしました。
二人が移り住んだ先は人魚町といわれ、それが訛って人形町と呼ばれました。また、女房人魚の抜け殻も薬種として高値で売れて、平次はますます儲かったとか。
二人が移り住んだ先は人魚町といわれ、それが訛って人形町と呼ばれました。また、女房人魚の抜け殻も薬種として高値で売れて、平次はますます儲かったとか。
本作の主人公である「釣舟の平次」の名は、当時「釣舟平次宿」と書いた厄除札が流行したことにちなむもので、作中でも平次が疫病神に魚をふるまったのでその名が厄除になるのだと噂が広まる場面があります。
▽関連
・人魚
冒頭の中洲新地廃止のくだりも実際の出来事だったり、お話自体も人魚や玉手箱の見世物が出ていたことが発想の根幹にあるようです。当時の流行などをもじった小ネタがいろいろ出てくるので是非原文で楽しんでいただきたいですね。
ほのぼのしたハッピーエンドにも癒されます。

コメント
コメント一覧 (6)
あの絵はこの作品の女郎屋で髪結ってもらってる場面を元にして描かれたものですね。
解説も大陸の書物を引いて人魚と人の性的な交わりについて言及するものなので、図らずも?女房人魚の話とリンクしてくる部分もありますね
異類のフロンティアになるというくだりが
リアルとファンタジーの交錯する面白さを感じますね
しかし二代目がバカ面とか人面魚に一目惚れして持って帰るとか生臭くて床入り不能とか
嫌すぎる舐められるお仕事とか
一皮剥けたら人間になってハッピーエンドとか
カオスの洪水にそんな感動はあっさり押し流されてしまうのでした
冒頭の舞台設定は本当に良いですよね。これをもとに綺麗なファンタジーが一本つくれそう
基本的にバカ話なんですが、人魚と平次の夫婦愛が最後まで確かなものなのでじんわりきちゃうんですよね。最後には浦島夫婦も出てきて勢い任せのハッピーエンドに持っていくし。こんな世界でくらい異類婚も睦まじく続いたっていいだろう、みたいな作者の気前の良さを感じますよね。
京伝先生、推せる……!
海女房は人形で、しかも漬け物石をいとも簡単にどけてしまうほどの怪力の持ち主なので、別物かと。